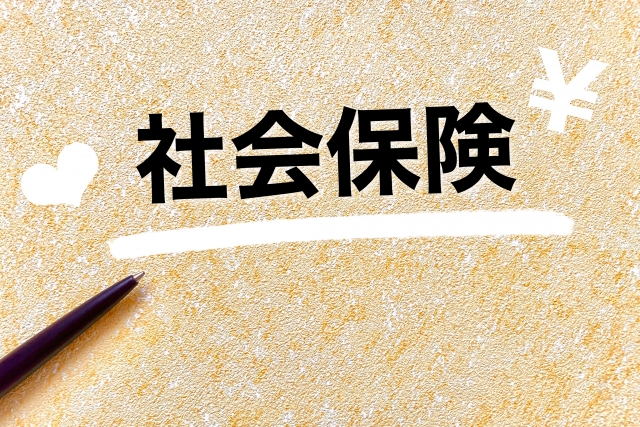人事労務担当者は、給与の額面だけではなく、そこから社会保険の会社負担、労災・雇用保険の会社負担のトータルで人件費を考えなければなりません。人件費にかかる保険料は会社にとって負担が大きいものです。今回は、令和7年度の社会保険料率と、変更点の多い育児介護関係について見ていきましょう。
2025(令和7)年度の社会保険料率はこう変わる!?
2025(令和7)年度の社会保険料率(健康保険料、介護保険料、雇用保険料)は次のように変更されます。
1.健康保険料
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料は都道府県によって料率が異なります。令和7年度の健康保険料率は、近畿地方では、大阪府・京都府・兵庫県・ 奈良県ではやや下がる一方、和歌山県ではやや上がる見込みです。
Ⅱ.介護保険料
全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料は全国一律です。令和7年度の介護保険料率が、今年度から0.01ポイント減少し、1.59%になります。
なお、各都道府県毎の健康保険料率や介護保険料率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページで確認することができます。
Ⅲ.雇用保険料
令和7年度の雇用保険料率は令和6年度と比べて、引き下げられる方針です。6年度の保険料率である1.55%(労使負担合計)から、0.1%引き下げて1.45% (労使負担合計)となります。
なお、雇用保険料率は、厚生労働省のホームページで確認することができます。
大阪府における変更前後の各料率は次のようになります。
【健康保険料・介護保険料】
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 健康保険料(大阪府) | 10.34% | 10.24% |
| 介護保険料(全国一律) | 0.60% | 0.59% |
【雇用保険料】
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 労働者負担 | 0.60% | 0.55% |
| 会社負担 | 0.95% | 0.90% |
※健康保険料率・介護保険料率は労使折半前
※令和7年度分は令和7年2月1日時点の予定のもの
2025(令和7)年4月より「出生後休業支援給付金」が創設されます
育児休業中に労働者に支払われる給付として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金があります。これに加えて、令和7年4月より、共働き・共育てをより推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していないなど一定の場合は本人のみでも可)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金に上乗せする形で休業開始時賃金日額の13%の「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
これにより、給付率が67%の出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせた給付率は80%(67%+13%)となります。育児休業等給付は非課税で、育児休業中は申出により健康保険料や厚生年金保険料も免除されるため、最大28日間は実質的に休業前の手取りの10割相当の給付を受けることができるようになります。
育児・介護休業法施行規則等の法改正は令和7年4月と10月の2回あります
育児・介護休業法施行規則等については、令和7年4月1日と令和7年10月1日施行の二度にわたる法改正となります。男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。今回の法改正も就業規則の見直しが義務化されているものがあります。
育児・介護関係の改正は基本的には労働者が育児や介護をしやすくする方向のものであるため、会社側からすると、改正がある度に会社にとっての負担は重くなってしまいます。
育児・介護関係について、事業主を支援する制度として「両立支援等助成金」がありますのでそちらをご活用されるとよいでしょう。
両立支援等助成金【育児休業等支援コース】
会社が育児休業の円滑な取得・復帰支援の取組を行い、育児休暇を3か月以上取得した従業員がいる場合、一定の要件を満たせば、育児休暇を取得時に30万円、復帰後に30万円の計60万円の助成金を受けることができます。
両立支援等助成金【出生時両立支援コース】
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、男性の場合など、連続5日以上の休暇を取得する場合、一定の要件を満たせば、20万円の助成金を受けることができます。
両立支援等助成金はここで紹介したコース以外にも様々なコースがあります。また、毎年変更が行われています。令和7年度(助成金情報は4月以降に公開)も要件や助成金額が変更になる場合がありますので、注意しておきましょう。
まとめ
令和7年度の社会保険料率と、変更点の多い育児介護関係について解説しました。社会保険料率の変更は、給与計算に必ず影響があるので、人事労務担当者は必ず把握しておかなければなりません。また、労働者が長期間安定して働いてもらうためには会社としての出産・育児・介護関係の環境整備は不可欠です。育児・介護に関する制度についてもぜひ知っておきましょう。